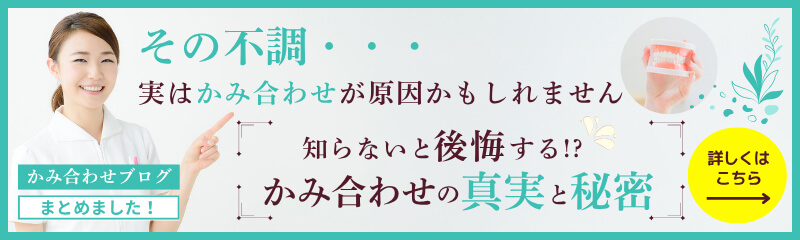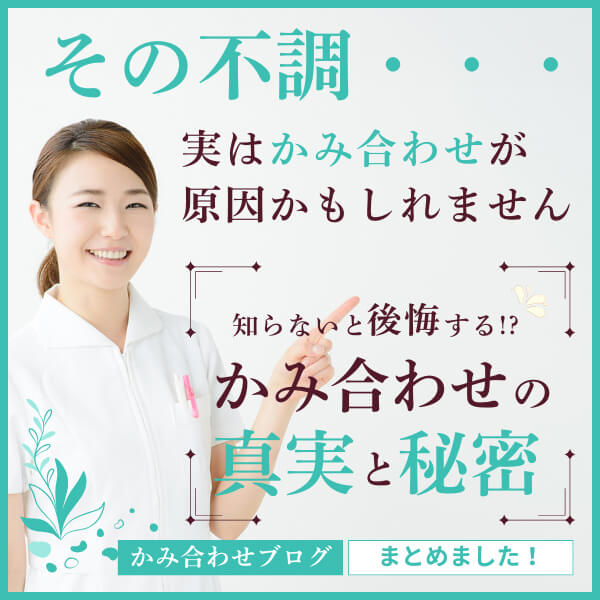1.はじめに:かみ合わせは「歯」だけの問題ではない
「咬合(こうごう)」とは、単に上下の歯が噛み合う関係を指す言葉ではありません。
人の体は、顎関節・筋肉・姿勢・呼吸・視線のバランスなどが緻密に連動しています。
したがって、咬合が乱れるということは「全身バランスの崩れ」と密接に関係しており、
その結果として首や肩のこり、頭痛、腰痛、さらには姿勢の歪みまで影響を及ぼすことがあります。
アールクリニックでは、咬合を“歯だけの問題”として捉えず、
全身との関係性を重視した「総合的な診査診断」を行っています。
2.咬合の乱れが全身に及ぼす影響
咬合の不調和は、まず顎関節周囲の筋肉バランスを乱します。
たとえば、右側でよく噛む人は、右の咀嚼筋(咬筋・側頭筋・内外側翼突筋)が過緊張を起こし、
左右の筋肉バランスが崩れることで、頭部の位置が傾き、頸椎(首の骨)のアライメントも乱れます。
この小さなズレが、背骨全体のねじれや骨盤の傾きを引き起こし、結果として「姿勢が悪い」「片方の肩だけが上がる」「腰が痛い」など、一見すると歯とは無関係に思える症状として現れるのです。
つまり、咬合の乱れとは“体のゆがみを引き起こすスイッチ”でもあります。
3.顎の位置が変わると、姿勢も変わる
人の頭部は約5〜6kgもの重さがあり、それを支える首や背骨には常に負荷がかかっています。
その頭の位置を決めているのが、実は「下顎の位置=顎位(がくい)」です。
顎位が前にずれると、頭部が前方に傾き、猫背姿勢になりやすく、
顎位が後方にずれると、頸部が反り返り、肩こりや緊張型頭痛の原因となることがあります。
アールクリニックでは、顎位を科学的に分析するためにCADIAX(キャディアックス)による顎運動解析を実施しています。
このデータにより、咀嚼筋や関節の動きがどのように連動しているかを可視化でき、咬合治療や矯正治療の計画に欠かせない情報となります。
4.「正しい咬合」とは何か?
理想的な咬合とは、単に歯がきれいに並んでいることではなく、「下顎が筋肉や関節に無理なく安定している状態」を指します。
それを実現するには、以下の3要素が重要です。
- 顎関節の安定(関節円板・下顎頭の正しい位置)
- 咀嚼筋のバランス(左右対称の筋活動)
- 咬合接触の調和(上下歯の接触タイミングが均等)
この3つが整って初めて、顎関節から全身までが調和する「生理的な咬合」が成立します。
見た目の歯並びだけを整えても、顎位がずれていれば、再び噛み合わせが崩れる可能性があるのです。
5.咬合と重心の関係
体の重心は、頭・背骨・骨盤・下肢の位置関係で決まります。
この中で、顎のわずかなズレが重心線を乱すことは意外と知られていません。
例えば、右側で多く噛む人は右肩が下がり、右骨盤が前方回旋しやすくなります。
逆に、左で噛む人は左側が下がる傾向があり、その結果、片足重心や歩行の癖が固定化していきます。
このように、咬合の偏りは下半身の動きにも影響するため、スポーツ選手がパフォーマンス向上のために咬合を調整するケースも増えています。
「よく噛める」ということは、「全身が安定する」ということでもあるのです。
6.かみ合わせを整えることの本当の意味
「かみ合わせを整える」とは、歯をまっすぐ並べるだけではなく、“体の軸”を正す治療でもあります。
アールクリニックの咬合治療では、
- セファロ分析による骨格的診断
- 顎運動検査による顎関節機能評価
- 咬合器を用いた再現模型分析
- 咬合紙やBruxCheckerによる接触パターン確認
といった多角的な検査を行い、「どの位置で咬むと全身が最も安定するか」を科学的に導き出しています。
つまり、咬合の改善は“全身の健康を整える第一歩”なのです。
7.まとめ:かみ合わせから始まる「全身の調和」
かみ合わせは、歯・顎・筋肉・姿勢・呼吸が連動する総合的なシステムです。
それがほんの少し乱れるだけで、全身のバランスが崩れることもあります。
だからこそ、単なる「歯並びの治療」ではなく、“体全体の機能を整えるための咬合治療”が求められます。
山口県宇部市の歯科・矯正歯科アールクリニックでは、咬合と全身のバランスを重視した診査診断を通じて、患者さま一人ひとりの自然で健康的な咬合を目指しています。
かみ合わせを整えることは、あなたの身体と心のバランスを整えること。
その小さな一歩が、全身の調和を生み出す大きな変化につながります。
📞 無料相談のご予約はこちらから
▶︎ お電話:0836-51-6480(ガイダンスで「1」を選択)
▶︎ ネット予約:https://reserve.dental/web/b6edc1-810
あなたの“かみ合わせ”が整うことで、きっと体も心も、軽やかに変わっていきます。