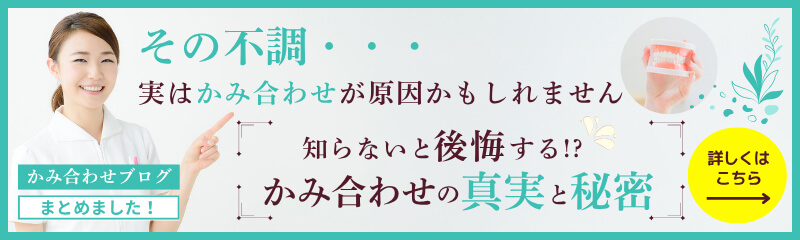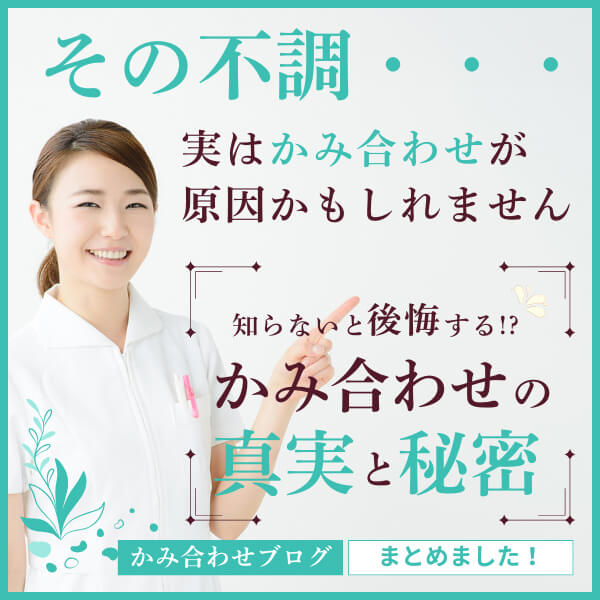はじめに
「朝起きると顎が疲れている」「肩や首がこっている」「歯がすり減ってきた気がする」──これらの症状に心当たりはありませんか?
その背景にあるのが 睡眠中の食いしばり(ブラキシズム) です。無意識のうちに強い力がかかるため、顎関節症の大きなリスク要因のひとつとなります。
今回の記事では、睡眠中の食いしばりと顎関節症の関係、そして予防・対策について詳しく解説します。
1. 睡眠中の食いしばりとは?
食いしばりは「起きているとき」と「寝ているとき」に分けられます。特に問題となるのは 睡眠時ブラキシズム です。
- 強い力で歯と歯を接触させる
- ギリギリと歯ぎしりをする
- 奥歯に大きな負担をかける
研究では、睡眠中の食いしばりは 自分の体重の2倍以上 の力がかかるとも言われています。これは顎の関節や筋肉に過剰な負荷を与え、慢性的な顎関節症を引き起こす原因になります。
2. 食いしばりが顎関節症を悪化させるメカニズム
睡眠中の食いしばりは、以下のような悪影響を及ぼします。
関節円板への負担
関節円板は顎の動きをスムーズにするクッションの役割を果たしています。強い圧力で変形やずれが生じると「カクカク音」や「口が開きにくい」などの症状が出ます。
咀嚼筋の緊張・疲労
無意識の緊張が続くことで筋肉が硬直し、顎やこめかみの痛み、頭痛・肩こりにつながります。
歯や骨のダメージ
歯のすり減り、知覚過敏、歯の破折、さらには歯周組織へのダメージが進行することもあります。
つまり、睡眠中の食いしばりは 顎関節症の「隠れた悪化因子」 といえるのです。
3. なぜ寝ている間に食いしばるのか?原因と背景
睡眠中の食いしばりは、単なるクセではなく複数の要因が絡み合っています。
- ストレスや心理的要因:日中の緊張が睡眠中に無意識の食いしばりとなって現れる
- かみ合わせや歯並びの不調:上下の歯の接触が不安定な場合、無意識に調整しようとする
- 生活習慣:アルコール、喫煙、カフェイン摂取がリスクを高める
- 睡眠の質:浅い眠りや無呼吸症候群などが影響するケースも
当院では、こうした要因を一つひとつ明らかにするため、科学的根拠に基づいた診査・診断 を重視しています。
4. 自宅でできる予防とセルフケア
睡眠中の食いしばりを完全に止めるのは難しいですが、習慣や生活を整えることで負担を減らすことができます。
寝る前のリラックス習慣
深呼吸、ストレッチ、軽い入浴で筋肉の緊張を和らげる。
寝姿勢の改善
横向き寝やうつ伏せ寝は顎に負担をかけやすいため、仰向け寝を意識する。
カフェインやアルコールの制限
寝る直前の摂取を控え、睡眠の質を整える。
日中の食いしばり意識
「上下の歯を離す」を意識するだけで筋肉の緊張が減る。
こうしたセルフケアを積み重ねることが、睡眠中の食いしばりの軽減につながります。
5. 歯科医院でできる専門的な対策
セルフケアだけでは不十分な場合、専門的なアプローチが必要です。
ナイトガード(マウスピース)
寝ている間に装着することで歯や関節への負担を軽減。オーダーメイドで快適に使用可能。
咬合診査と調整
セファロ分析、CT撮影、CADIAXによる顎運動解析などを行い、咬合不調和がある場合には矯正治療や補綴治療で改善。
ボツリヌス療法
咬筋の過剰な緊張を抑制し、食いしばりを軽減する治療。
かみ合わせ治療との連携
当院では「治療ゴールを患者さんと共有する」ことを重視し、シミュレーションを使って将来の口元の変化を一緒に確認します。
これにより「なぜ治療が必要なのか」を納得した上で進められるのが大きな特徴です。
6. 顎関節症を放置しないために
睡眠中の食いしばりを軽く考えて放置すると、症状は慢性化し、改善に時間がかかるようになります。
- 顎の関節に構造的な変化が起こる
- 歯の摩耗や破折が進む
- 全身の不調(肩こり、頭痛、腰痛)に発展する
特に、かみ合わせの不調や顎関節症の既往がある方は、早期の対策が重要です。
7. まとめ|顎関節症無料相談のご案内
睡眠中の食いしばりは、顎関節症を悪化させる大きなリスク要因です。しかし、生活習慣の改善と歯科医院での専門的な対策を組み合わせれば、症状の軽減や進行予防が可能です。
山口県宇部市の歯科・矯正歯科アールクリニックでは、
- 科学的根拠に基づいた診査診断
- CT・セファロ・CADIAXを用いた精密検査
- 治療後を見据えたシミュレーションとゴール共有
を大切にし、患者さまが納得して治療を進められる体制を整えています。
もし「朝起きると顎が疲れる」「歯がすり減ってきた」などのお悩みがある方は、まずは一度 顎関節症無料相談 にお越しください。あなたに合った最適な解決方法をご提案いたします。