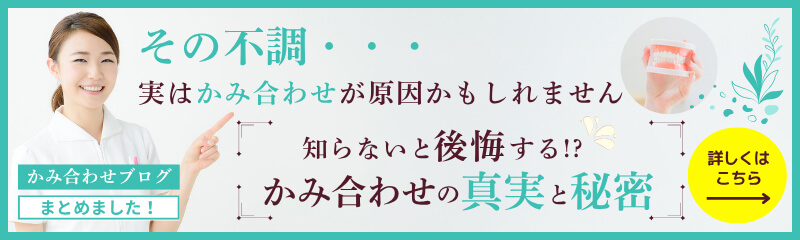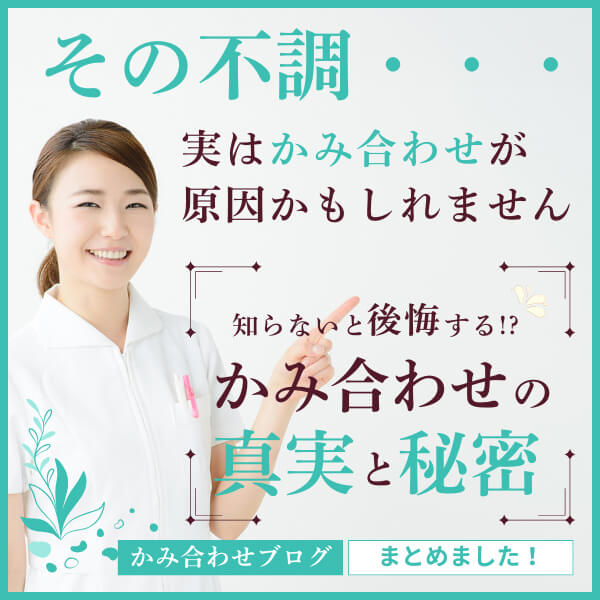はじめに:眠ったはずなのに顎が重い?
「朝起きると顎がだるい」「こめかみが張っている」「口が開きにくい」。
そんな経験が続く方は、睡眠中の無意識な噛みしめや顎関節症が隠れているかもしれません。
眠って体を休めるはずの時間に、なぜ顎が疲れてしまうのか?
今回は「顎関節症と睡眠の関係」に注目し、その背景と改善のためのポイントを解説します。
睡眠中に起こる“噛みしめ”と“歯ぎしり”
睡眠時は自分の意思ではコントロールできないため、無意識に強い力で歯を噛みしめている方が少なくありません。
- 歯ぎしり(グラインディング):ギリギリと歯をこすり合わせる
- 噛みしめ(クレンチング):音は出ないが強く食いしばる
これらが繰り返されると、顎関節や咀嚼筋に過剰な負担がかかり、朝の「顎の疲れ」「こわばり」として現れます。
なぜ眠っている間に噛みしめるのか?
原因は一つではなく、いくつかの要素が複雑に絡み合います。
1. ストレス・心理的緊張
日中のストレスが夜に噛みしめとして現れることがあります。
2. かみ合わせの不均衡
歯の接触が安定していないと、無意識に補正するように噛みしめが起きやすくなります。
3. 睡眠の質の低下
眠りが浅いと筋肉が緊張状態のままになりやすい傾向があります。
4. 生活習慣
カフェイン摂取、寝る前のスマホ、姿勢の悪さも要因です。
朝の顎の疲れがもたらす影響
「朝だけだから大丈夫」と油断してはいけません。放置すれば…
- 顎の痛みや開口障害
- 慢性的な頭痛・肩こり
- 歯の摩耗や欠け
- 顔のゆがみや表情筋のこわばり
と、全身の不調へと広がることがあります。
当院が行う診査・診断と治療の流れ
顎関節症を正しく治療するためには、**「科学的根拠に基づいた診査・診断」**が欠かせません。
アールクリニックでは、次の流れでしっかりと原因を特定します。
1. 問診・写真診査
生活習慣や既往歴を確認し、顔貌・口腔内を撮影します。
2. 模型診査・咬合器分析
歯型を採り、上下の噛み合わせのずれを立体的に解析します。
3. 画像診査
パノラマX線・セファロ・CTなどで骨格や関節の状態をチェック。
4. 顎運動解析(CADIAX)
関節の動きを精密に記録し、クリック音や動きの偏りを可視化します。
5. 筋触診・BruxChecker
筋肉の緊張や歯ぎしりの痕跡を確認します。
これらを総合的に分析し、「朝の顎の疲れ」がなぜ起こるのかを科学的に突き止めたうえで、治療ゴールを患者さんと共有します。
主な治療法
- スプリント療法(夜間マウスピースで筋肉・関節を保護)
- 矯正治療や補綴治療によるかみ合わせ改善
- 生活習慣やセルフケアの指導
自宅でできるセルフケア
- 就寝前のストレッチや深呼吸でリラックス
- 枕の高さを調整し、首肩の緊張を軽減
- 寝る前のスマホ・PC作業を控える
- 「上下の歯は離しておく」意識を日中から習慣化
ただし、セルフケアだけでは不十分なことが多く、精密な診断と治療が不可欠です。
まとめ:朝の違和感を軽視しないで
- 朝の顎の疲れは顎関節症のサインかもしれない
- 睡眠中の噛みしめ・歯ぎしりが大きな原因
- 放置すると全身に影響が及ぶ可能性あり
- 科学的診査と総合診断で原因を特定し、根本改善を目指せる
山口県宇部市の歯科・矯正歯科アールクリニックでは、顎関節症やかみ合わせに関するご相談を無料で承っています。お気軽にお問い合わせください。