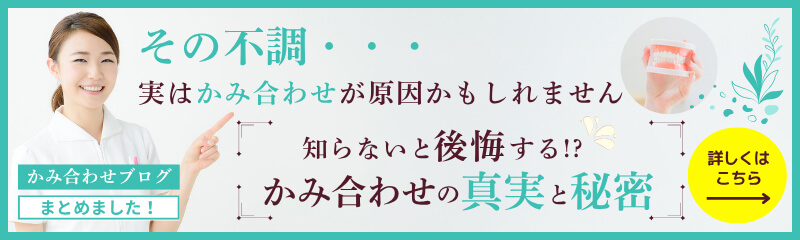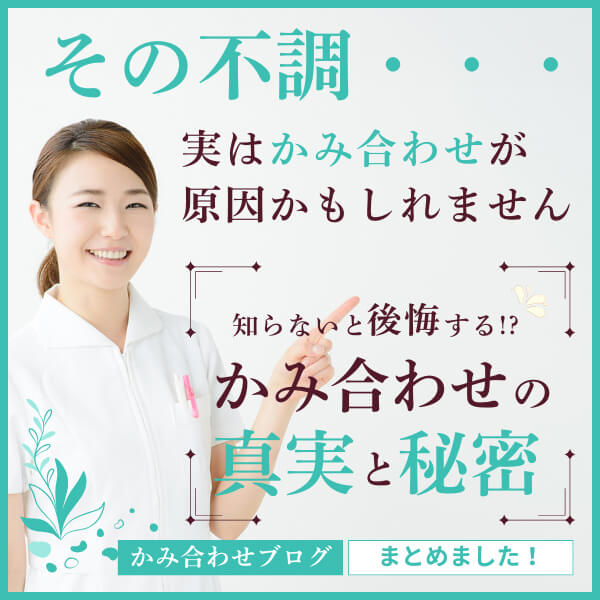かみ合わせ治療では、歯や顎の位置だけでなく、周囲の筋肉の状態を知ることがとても大切です。歯科医院で行われる「筋触診」は、顎やその周囲の筋肉の硬さや痛みの有無を手で確認する診査法です。本記事では、筋触診の重要性や方法、そこから分かることについてわかりやすく解説します。
1. 筋触診とは?その目的と役割
筋触診(きんしょくしん)は、歯科医師が指で顎やその周囲の筋肉を軽く押したりなぞったりして、硬さや圧痛(押したときの痛み)の有無を確認する診査法です。
顎関節症やかみ合わせの乱れは、噛む筋肉や首の筋肉に大きな影響を与えます。筋触診は、顎やかみ合わせの不調の原因を探るための重要な手がかりとなります。
特に次のような症状がある方には、筋触診の結果が診断のヒントになります。
- 顎がカクカク鳴る
- 口を大きく開けにくい
- 噛むときや顎を動かすと痛みが出る
- 慢性的な肩こりや頭痛がある
2. どの筋肉を調べるの?
筋触診では、主に咀嚼(そしゃく)筋と呼ばれる「噛むための筋肉」と、首や肩の筋肉を診ます。代表的な部位は以下の通りです。
- 咬筋(こうきん):頬のあたりにある大きな筋肉。噛む力のメインを担います。
- 側頭筋(そくとうきん):こめかみから頭頂部にかけて広がる筋肉。奥歯を噛みしめると盛り上がる部分です。
- 内側翼突筋(ないそくよくとつきん)・外側翼突筋(がいそくよくとつきん):顎の内側にある筋肉。顎の前後・左右の動きに関与します。
- 首や肩の筋肉(胸鎖乳突筋や僧帽筋など):かみ合わせの不調が続くと、首・肩の筋肉にも負担がかかりやすくなります。
これらの部位を順に押していき、左右の差や筋肉の硬さ、痛みの有無を調べます。
3. 筋触診でわかること
筋触診によって分かることは、主に以下の3つです。
①筋肉の緊張度合い
筋肉が硬くなっていると、噛み合わせが不安定になっている可能性があります。慢性的に噛みしめるクセがある方や、睡眠中の歯ぎしりのある方では、咬筋や側頭筋の緊張が強く出やすいです。
②左右差の有無
片方の筋肉だけ硬い、痛いといった場合は、顎の動きやかみ合わせに偏りがある可能性があります。
③顎関節や首・肩の筋肉との関連
噛む筋肉が緊張すると首や肩の筋肉にも負担がかかり、肩こりや頭痛を引き起こすことがあります。逆に首の筋肉のバランスが崩れると顎に負担がかかることもあり、全身的な影響を把握することができます。
4. 筋触診は総合診断の一部
筋触診は単独の診査ではなく、総合診断の一部として行います。
かみ合わせ治療の現場では、次のような流れで資料を集めます。
① 医療面接や顔貌・口腔内所見の診査(写真撮影)
② 模型診査(顎位の採得、咬合器への付着)
③ X線診査と分析(パノラマ、セファロ、CTなど)
④ 顎運動検査(CADIAXなど)
⑤ 筋触診
⑥ BruxChecker(ブラキシズムの確認)
この中で筋触診は、「顎の動きの質と筋肉の状態」を把握するための重要な検査です。患者さん自身が感じている不快症状と、客観的な診査データを結びつける役割もあります。
5. 筋触診から治療方針を立てる
筋触診の結果は、かみ合わせの調整やスプリント(マウスピース)治療の方針決定に活かされます。例えば…
咬筋が強く緊張している場合
→ 噛みしめや歯ぎしりの改善を目的としたスプリント治療を優先
顎の開閉時に特定の筋肉が痛む場合
→ 顎関節の位置や動きの改善を目指した治療を検討
左右の筋肉バランスが崩れている場合
→ 噛む力の偏りを減らす矯正的アプローチや補綴治療を行う
こうした方針を立てるために、筋触診は欠かせない情報を与えてくれます。
6. まとめ:かみ合わせ治療に欠かせない筋触診
筋触診は、顎や噛む筋肉の状態を直接確かめるシンプルかつ重要な検査です。
痛みや違和感の原因を明らかにするだけでなく、かみ合わせの乱れが全身のバランスに及ぼす影響も知ることができます。
山口県宇部市の歯科・矯正歯科アールクリニックでは、筋触診を含む多角的な資料採得を行い、患者さん一人ひとりに合ったかみ合わせ治療の方針を立てています。顎やかみ合わせに違和感を感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。