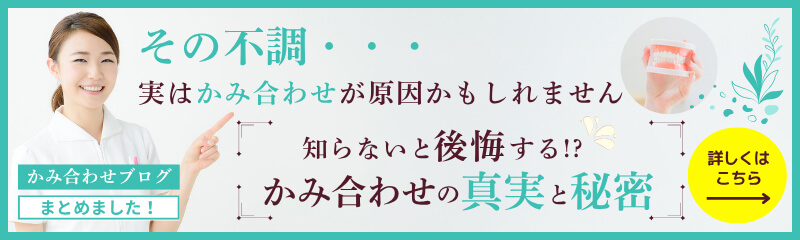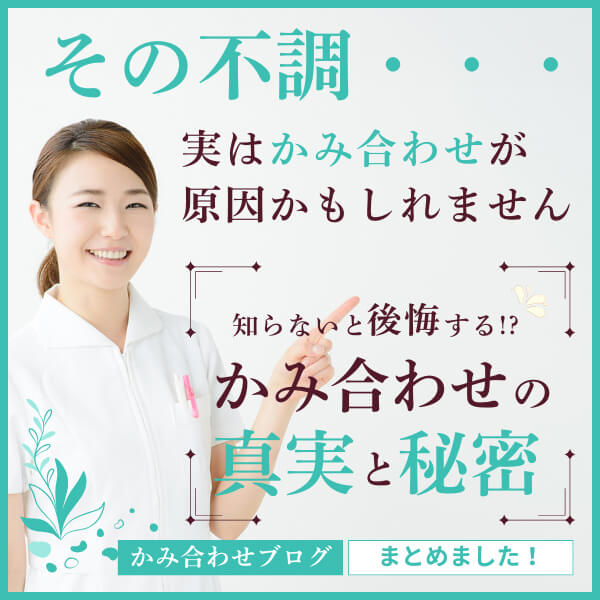はじめに:「模型診査」って聞いたことありますか?
歯科医院での検査といえば、レントゲンや口腔内写真を思い浮かべる方が多いかもしれません。でも、実は**歯型模型(歯列を立体的に再現した模型)**による診査、つまり“模型診査”がとても重要な役割を果たしているのです。
今回は「なぜ模型診査が必要なのか?」という素朴な疑問に、かみ合わせ治療の視点から丁寧にお答えしていきます。
1. 模型診査とは?目で見えない「かみ合わせのズレ」を可視化
模型診査とは、患者さんの歯列の状態を模型として再現し、上下の顎のかみ合わせを診断することです。ここでは、実際の咬合状態を客観的に再現し、次のような情報が明らかになります。
- 上下の歯がどう噛み合っているか
- 顎の動きや噛む位置にズレがないか
- 咬合接触のバランスや偏り
- 咬合高径(かみ合わせの高さ)の評価
これらは肉眼や写真では見えにくく、模型診査によって初めて“見える化”される情報です。
2. 模型診査の流れ:選べる手法で、より快適に・より正確に
当院では、従来のシリコン印象に加えて、口腔内スキャナーによるデジタル印象という選択肢もご用意しています。さらに、必要に応じてそのデータをもとに3Dプリンターで模型を造形することも可能です。
目的や症例に応じて、患者様の負担や精度のバランスを考えながら、最適な手法を選択しています。
模型診査の主な流れは次の通りです:
①印象採得(シリコン or 口腔内スキャナー)
従来の型取りに加え、スキャナーでの印象採得も可能です。快適さや嘔吐反射への配慮として選ばれることもあります。
②咬合採得
「噛んだ状態(下顎位)」を正確に記録します。RP(リファレンスポジション)やICP(習慣性咬合位)などの評価が重要です。
③フェイスボウトランスファー
頭部との関係性を再現するため、顎の位置情報を咬合器に正確に反映させます。
④ 模型造形・咬合器装着
シリコン印象から石こう模型を製作するか、スキャンデータを用いて3Dプリンターで模型を造形し、咬合器に装着します。
このように、手法を柔軟に選択しながら、高精度な咬合再現を行っています。
3. 模型診査で分かる“ズレ”と“問題点”
模型診査では、以下のようなかみ合わせの問題が明らかになります。
早期接触(Premature Contact)
一部の歯だけが早く当たることで、顎や筋肉に負担が集中します。
咬頭干渉(Cuspal Interference)
咬頭が不自然にぶつかることで、下顎の動きを制限してしまう状態です。
咬合支持の喪失(Loss of Occlusal Support)
奥歯の咬合が崩れている場合、前歯や関節へと負担が移行します。
咬合平面の傾きや不均衡
左右の高さの差などにより、顔や姿勢のバランスに影響が及ぶこともあります。
こうした咬合異常は、普段の診察やレントゲンでは見逃されることもあるため、模型による立体的な診査が非常に重要になります。
4. 総合診断の中核を担う「模型診査」
当院では、模型診査を「総合診断」の一部として重視しています。セファロ(頭部X線)やCT、CADIAX(顎機能検査)、姿勢写真などと組み合わせ、より正確な診断を実現しています。
とくに3Dプリンター模型は、複数回の比較や再診時の検証に役立つだけでなく、患者様への説明にも有用です。再現性に優れ、治療前後の変化も客観的に示すことができます。
まとめ:模型診査は“かみ合わせの現在地”を教えてくれる
模型診査は、歯や顎の状態を立体的に再現することで、噛み合わせの“見えないズレ”を見つけ出すための重要なステップです。
山口県宇部市の歯科・矯正歯科アールクリニックでは、従来の方法に加えてデジタル印象や3Dプリンター模型といった先端技術も取り入れ、患者様それぞれに最適な診断方法を選択しています。
「噛みにくい」「顎が疲れる」「食いしばりが気になる」など、ちょっとした不調も、実は“かみ合わせ”が原因かもしれません。
まずは模型が語る“あなたの咬合の姿”を、一緒に確認してみませんか?